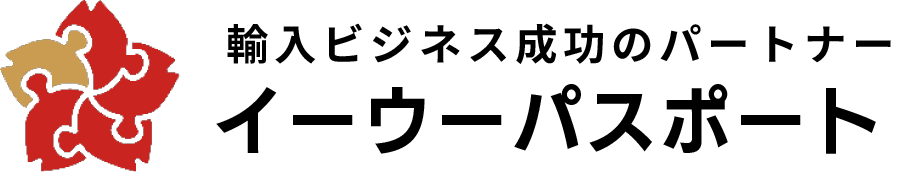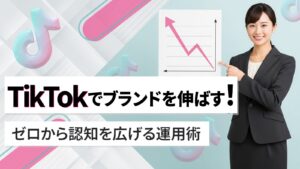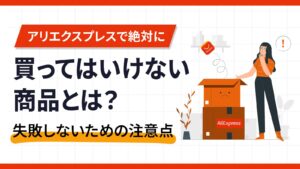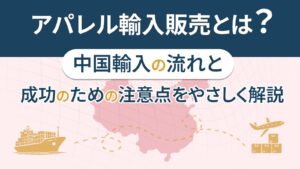「中国輸入で仕入れた商品が不良品ばかりで販売できない」
「中国のサイトで購入した商品が輸入手続きに通らず、廃棄されてしまった」
新しいことに挑戦すると、想定外のトラブルに見舞われることがありますよね。
中国輸入にも、まだ経験の少ない初心者に起こりがちなトラブルがあります。場合によっては訴えられたり、大きな損失を被ったりするケースもあるため、全く知識のない状態で参入するのは危険です。
中国輸入でよくあるトラブルは、前もってトラブルの内容と対策方法を知り、実践することで防ぐことができますよ。
この記事では、中国輸入でよくあるトラブルとその対策について解説します。
この記事で紹介している対策を実践し、安全に中国輸入ビジネスに取り組みましょう。
中国輸入でよくあるトラブルと効果的な対策6選
さっそく中国輸入でよくあるトラブルとその対策について紹介します。
中国輸入でよくあるトラブルは次の6つです。
- 仕入れた商品の品質が悪い
- 輸入禁止商品や輸入規制のある商品を仕入れてしまう
- 知的財産権を侵害している商品を仕入れてしまう
- 中国の物流ストップによる在庫切れ
- 為替変動による仕入れ価格の高騰
- 言語や商文化の違いによるトラブル
どのトラブルも事前のリサーチや代行会社の活用により防ぐことができます。
それぞれの内容をチェックし、実践していきましょう。
①仕入れた商品の品質が悪い

中国から仕入れた商品の品質が悪いと、返品やクレームなどのトラブルにつながります。
品質トラブルを回避するには、次の2つの方法があります。
- サンプルを発注する
- 代行会社に検品を依頼する
まず、まとまった数量を発注する前にサンプルをいくつか発注し、品質に問題がないかチェックしましょう。
サンプルが届いたら、
- 画像と実物で色の違いがないか
- 壊れやすい部分がないか
- ほつれている部分がないか
など、お客様の目線に立ち、クレームにつながりそうな部分がないかチェックしましょう。前もってサンプルを確認することで、想定外の品質トラブルを回避できます。
販売開始後は、代行会社に商品の検品を依頼すると安心です。
副業で中国輸入をしている場合やスタッフが少ない場合、毎回すべての商品を検品するのは難しいでしょう。代行会社にすべての商品を検品してもらうことで、不良品が購入者のもとに届くのを防げます。
代行会社に検品を依頼する時は、重点的にチェックしてほしいポイントを共有しておきましょう。商品ごとに不良の出やすい部分が異なるので、具体的に指示を出すことで見落としを防げます。
②輸入禁止商品や輸入規制のある商品を仕入れてしまう

輸入禁止商品や輸入規制のある商品を誤って購入してしまうと、輸入手続きに通らず、仕入れられない場合があります。
輸出入のルールは国によって異なります。中国では輸出可能でも、日本では輸入不可というケースがあるので、注意が必要です。購入した商品が輸入手続きに通らなかった場合、購入した商品を受け取ることはできず、次のような対応がとられます。
- 販売元に返送する
- 税関で廃棄する
輸入禁止商品や輸入規制のある商品を誤って購入しないよう、商品を仕入れる前に輸入禁止商品や輸入規制のある商品ではないことを確認しましょう。
輸入禁止商品は関税法を始め複数の法律で定められており、税関のサイトより確認できます。
海外で購入したギターが、ワシントン条約で輸入規制されている材質を使用しており輸入できなかった例もあります。一見問題のなさそうな商品でも、思わぬ理由で輸入手続きがストップしてしまう場合があります。必ず事前に確認しておきましょう。
③知的財産権を侵害している商品を仕入れてしまう
- 有名ブランドの偽物
- 許可を得ずにアニメのキャラクターを使用した商品
上記のような知的財産権を侵害している商品を仕入れて、トラブルになるケースがあります。
知的財産権は、人間の創造的活動によって生み出されたものに発生する権利を指し、次のようなものがあります。
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 著作権
- 商標権
知的財産権を侵害する商品を販売した場合、訴訟などの大きなトラブルに発展するおそれがあり、大変危険です。
知的財産権を侵害しないための対策として、次の3つがあります。
- 仕入れる前に特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で確認する
- 専門家(弁護士や弁理士)に相談する
- ノンブランド商品のみを仕入れる
商品を仕入れる前に、特許庁の特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で知的財産権の申請の有無を確認しましょう。
特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」は、無料で特許情報を検索・閲覧できるサービスです。
「J-PlatPatで調べてもよく分からない」「このまま進めていいのか不安」という方は、専門家(弁護士や弁理士)に相談するのがおすすめです。費用は掛かりますが、専門家に確認することで安全にビジネスに取り組めます。
また、ノンブランド商品に絞って仕入れを行うのも有効です。
最初から有名なメーカーやブランドの商品を仕入れなければ、偽物や模造品によるトラブルに巻き込まれることはありません。知的財産権の侵害によるリスクを最小限にしたい人は、ノンブランド商品を中心に仕入れましょう。
③中国の物流ストップによる在庫切れ

中国では春節と国慶節という祝日に合わせて、多くの企業が長期連休をとります。
中華圏における旧暦の正月のこと。中国では旧正月を盛大に祝う風習がある。
日程は毎年変わり、だいたい1月下旬~2月中旬頃に1週間ほど連休になる。
中国の建国記念日で、春節に次ぐ伝統的な祝日。毎年10月1日から1週間は連休期間となる。
中国の物流が一斉にストップするため、発注のタイミングを誤ると商品が納品されず、在庫切れを起こしてしまうことも。
在庫切れを起こすと、販売機会損失により売上が大幅に落ちてしまいます。
中国の大型連休による在庫切れ対策として、前もって中国の大型連休のスケジュールを把握し、連休に入る前に在庫を確保しましょう。
⑤為替変動による仕入れ価格の高騰

中国輸入では為替の変動により仕入れ価格が上がり、利益が確保できない場合があります。
為替には地域の紛争や政治的要因などさまざまな要素が影響し、世界情勢によって大きく変動します。中国輸入ビジネスで収益を上げるためには、為替の状況を常に意識しておくべきです。
過去に仕入れた実績のある商品でも、仕入れるタイミングによっては赤字になってしまう可能性があります。仕入れを行う際は、為替情報をチェックし、利益を確保できるか確認しましょう。
⑥言語や商文化の違いによるトラブル
日本と中国では言語や商文化が異なるため、契約内容や取引条件の解釈が食い違い、トラブルに発展する場合があります。
トラブルを回避するため、中国の言語や商文化について知識を得ておきましょう。また、日本人は曖昧な表現を好む傾向がありますが、中国企業と契約する時にはこちらの要望や取引条件をはっきりと伝えることが大切です。
中国語や商文化の勉強まで手が回らないという方は、中国語や中国の商文化に詳しい輸入代行会社の活用もおすすめです。
経験豊富な代行会社はトラブル回避のために押さえるべきポイントを把握しているため、安心して中国輸入ビジネスに取り組めます。
中国輸入代行会社のイーウーパスポートでは、全拠点に日本人が常駐。
価格交渉などのやり取りは現地スタッフが代行するので、中国語が分からなくても仕入れが可能です。
中国輸入に関するご相談やご質問があれば、下記よりお問い合わせください。
まとめ【中国輸入のトラブル回避には事前の対策が大切】
本記事では、中国輸入でよくあるトラブルとその対策について解説しました。
中国輸入でよくあるトラブルとその対策
- 品質トラブル:事前にサンプルを取り寄せて品質をチェックする
- 輸入禁止商品:仕入れ前に税関のサイトで輸入禁止商品でないことを確認する
- 知的財産権の侵害:仕入れ前に特許庁のサイトで知的財産権の申請の有無を確認する
- 中国の物流ストップによる在庫切れ:中国の大型連休の前に在庫を確保しておく
- 為替変動による赤字:常に為替情報にアンテナを張っておく
- 言語や商文化の違い:中国の言語や商文化に精通している輸入代行会社を活用する
中国輸入でよくあるトラブルは、事前に対策することで防ぐことができます。
この記事で紹介した対策を実践し、安全に中国輸入ビジネスを伸ばしていきましょう!
上記の対策をしても不安という方は、ぜひイーウーパスポートをご利用ください。
イーウーパスポートではお客様1人1人に専任スタッフがつき、ビジネスをサポート。
トラブル時には24時間以内に対応いたします!
食品衛生法やワシントン条約にも対応しておりますので、輸入許可が下りないトラブルを回避できます。
中国輸入に関するご相談やご質問は、下記よりお気軽にお問い合わせください。